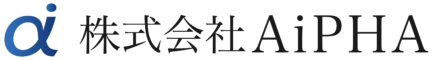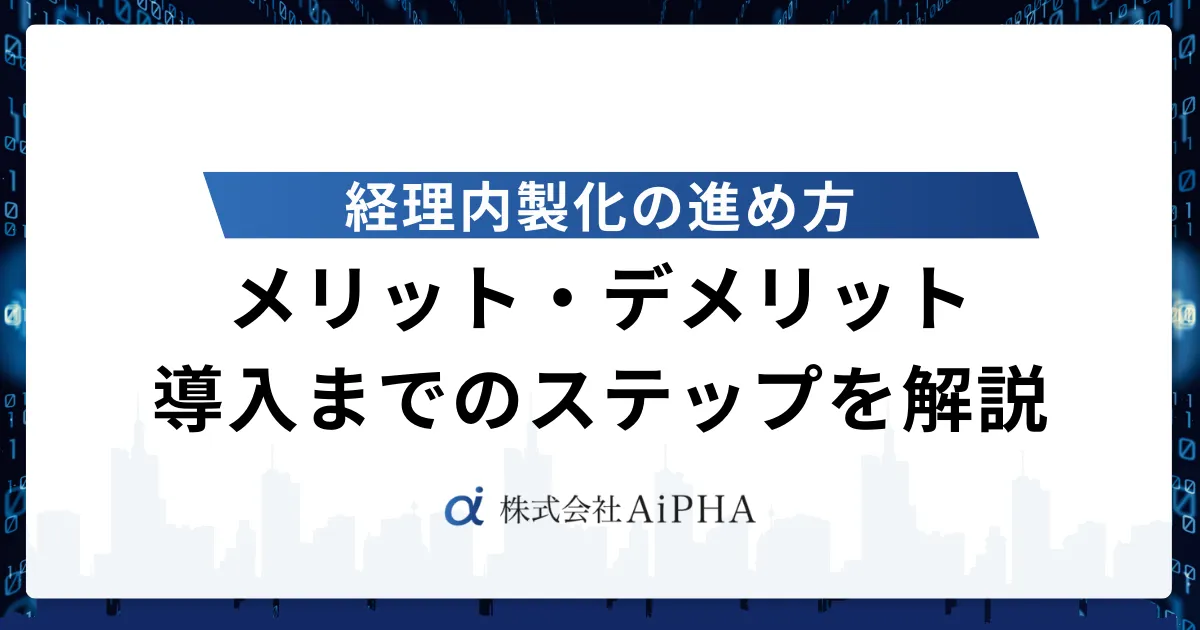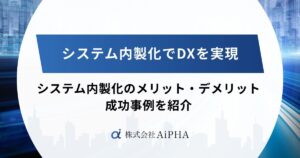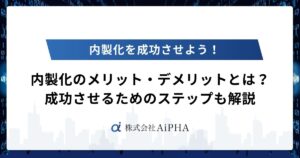経理の外注化は、業務を効率化できる一方でコストがかかることや、スピード感に欠けるといったデメリットがあります。
限られた予算の中でプロジェクトを運営する中、経理にかかるコストは決して無視できるものではありません。
しかし、これまで外注してきた経理業務を内製化しようとしても、何から手を付ければ良いのか不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では、経理内製化の進め方や成功させるための3つのポイントを紹介します。
経理の内製化を促進し、自社の経営を強化したい方は、ぜひ最後までお読みください。
 AiPHA代表 佐伯
AiPHA代表 佐伯「何から手を付ければ良いのかわからない」とお困りではありませんか?
現状分析から段階的な内製化プランまで、お客様に合わせてご提案いたします。
経理の内製化とは?
経理の内製化とは、これまで外部の税理士や経理代行会社に受託していた業務を自社内で完結できるよう、運用体制を切り替えることです。
単に自社で帳簿をつけるだけでなく、請求書発行、入金管理、経費精算、支払い業務、月次・年次決算といった一連の経理プロセスを社内で完結させます。
経理を内製化することで、意思決定後に迅速に実行へ移せるだけでなく、トラブルに対しての迅速な対応やセキュリティ、ガバナンス強化につながります。
また、これまで外注化していたコストを新規事業や採用の強化に回せるのもメリットです。中小企業やスタートアップでは、経理の透明性や柔軟性を重視するために、内製化への関心が高まっています。
内製化を進めるには、人員確保や社内ノウハウの蓄積だけでなく、適切なITツールの選定が不可欠です。適切なITツールを使用することで、業務効率化や長期コスト削減に貢献します。
経理内製化は、経理判断を自社で掌握し、構築するための重要な取り組みといえるでしょう。
以下の記事では、企業の成長促進にDXの内製化が必要な理由を解説しているので、あわせてご覧ください。
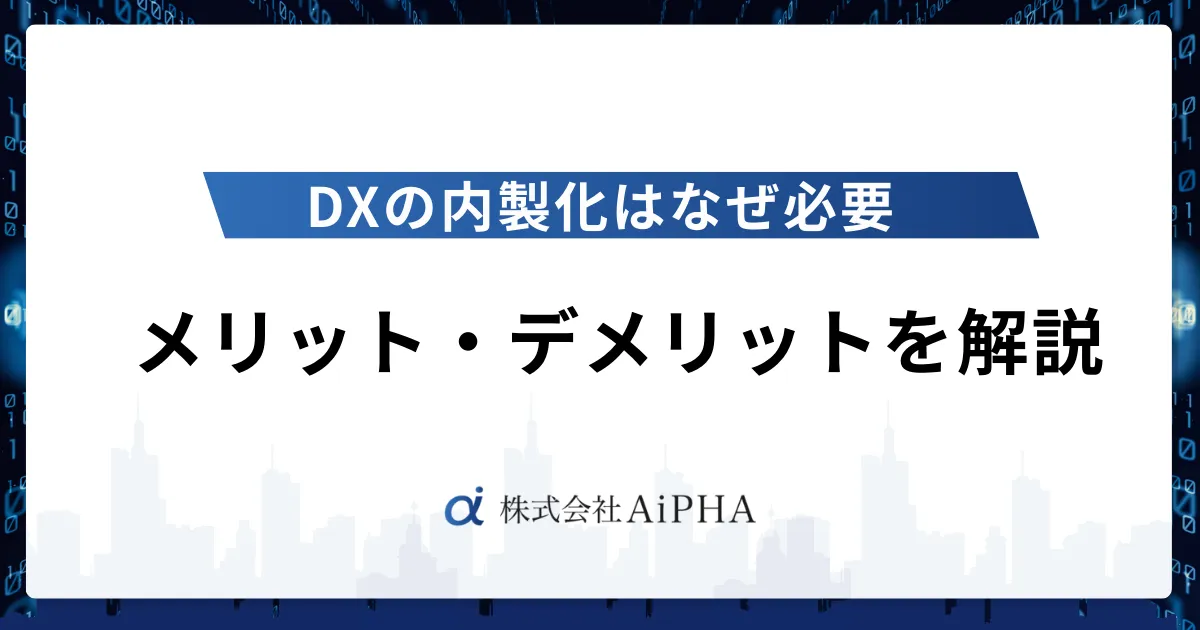
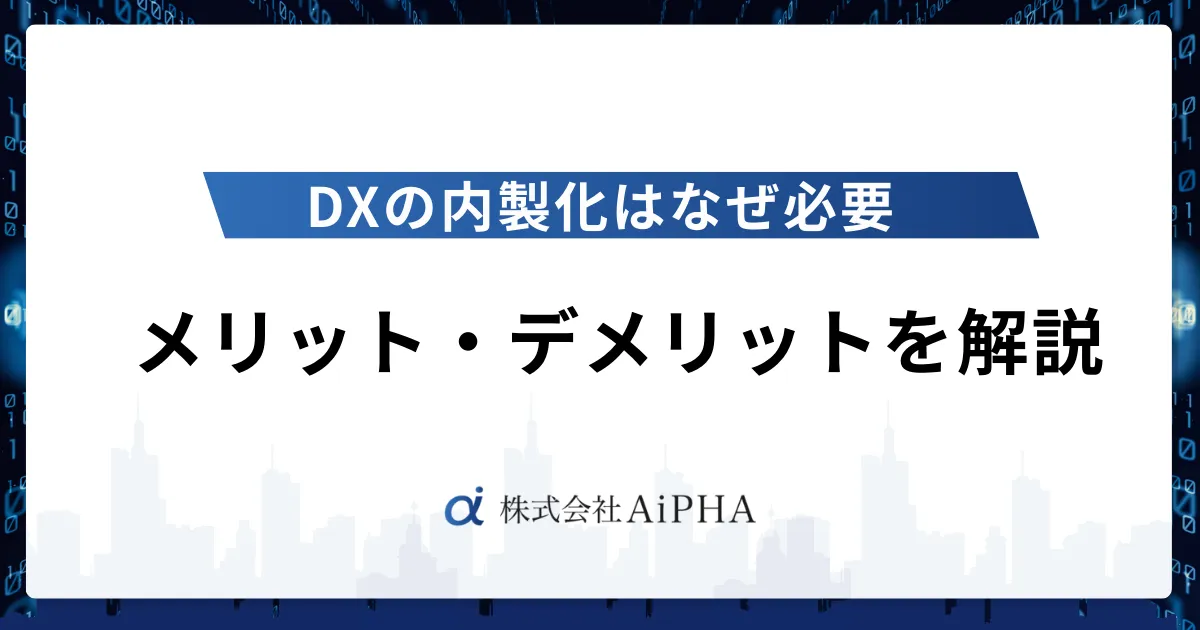
経理を内製化するメリット
経理の内製化には、次のようなメリットがあります。
これらのメリットを理解し、経理の内製化を進めていきましょう。
コストの最適化
経理を外注すると一見効率的に見えますが、実際は社外とのやりとりや契約更新、トラブル対応などで見えないコストが増えることがあります。外部委託では毎月の費用がかかるうえ、担当者の対応次第ではトラブルや手間が増えるリスクもあります。
経理を内製化することで、業務に見合った人員を配置し、必要に応じて業務を調整できるため、無駄なコストの削減が可能です。
内製化には採用や教育コストがかかるものの、長期的視点で捉えたときに社内ノウハウや組織力の強化につながります。
業務効率の向上
内製化により、経理業務に関する情報がリアルタイムで把握できるようになります。
外部委託の場合、どうしても情報共有されるまでにタイムラグが生じる傾向があります。しかし、内製化すれば、早急に確認したい数値やイレギュラー処理を迅速に行えるでしょう。また、部門間の情報連携もスムーズになり、業務の二度手間が削減されるのもメリットです。
たとえば、営業担当者が取引先への入金状況をすぐに確認したい場合、内製化されていれば経理担当者に直接聞くか、共有されているシステムで即座に確認できます。
経理の内製化を促進できれば、日々の業務効率を高めるだけでなく、経営のスピードアップにも直結するでしょう。
業務ノウハウの社内蓄積
経理を内製化すれば、業務ノウハウを社内に蓄積でき、外注で起こりがちなブラックボックス化を防げます。
仕訳から決算・申告まで自社で完結できる体制を作ることで、担当者のスキル向上や業務マニュアルの改善が進み、属人化の防止と組織全体の成長につながります。
財務状況の把握は、組織を守るために必要な知識です。経理の内製化における業務ノウハウの蓄積は経理体制の基盤といえます。



内製化で外注コストを削減しつつ、業務ノウハウの社内蓄積を実現できます。最初は外注しつつ、徐々に内製化するのもひとつの方法です。
経理を内製化するデメリット
経理の内製化を実施前にデメリットを把握しておく必要があります。
経理内製化のデメリットは以下の3つです。
経理の内製化には人件費やシステム導入の発生や、業務が非効率になるリスクも視野に入れなければいけません。
デメリットを理解し、経理の内製化における失敗を防ぎましょう。
初期コスト(人件費、システム導入費)の発生
経理の内製化には、人件費やシステム導入費に加え、教育にかかる時間などのコストもかかります。
経理業務は専門性が高いため、経験や資格を持つ人材の採用競争が激しく、採用に時間がかかる場合があります。とくに会社規模の小さいベンチャーや、スタートアップ企業は大手企業に比べて、人材採用の魅力が低くなりやすいため、優秀な人材の確保が難航する懸念があります。
また、システム導入や保守で発生する出費は無視できない負担です。回収目標を立てても思うように内製化が進まず、初期コストを回収できないケースもあるため、内製化は慎重に検討する必要があります。
業務が属人化するリスク
内製化を実施したことで、経理業務が特定の担当者に依存してしまい、細かい変更やルールをチーム全体で把握できなくなるケースがあります。規模の小さいベンチャーやスタートアップでは、数名の担当者が経理全般を担うことも珍しくありません。
業務が属人化すると、担当者が休職もしくは退職した場合に月次決算が遅延したり、誤った金額で処理を進めてしまったりするリスクがあります。
業務負担の増加が予想される場合も、経理の内製化は慎重に検討する必要があります。
業務が非効率になるリスク
内製化を安易に進めることで、かえって業務の非効率化を招く可能性があります。
担当者に十分な知識や経験がない場合、ミスの増加や手戻りの発生、失態による大きな損害を被る可能性があります。支払いミスによる信用失墜や、給与計算ミスによる従業員とのトラブルが発生する恐れがあるでしょう。
また、内製化にはシステム導入のコストや運用の手間が発生するため、社内体制を把握した上で実施する必要があります。
リスクを回避するには、業務フローの標準化や適切なITツールの選定と活用、担当者のスキルアップ支援など、長期的な視点で経理体制を強化することが大切です。
経理内製化の進め方
経理の内製化は一度にすべてを切り替える必要はありません。内製化を成功させるには、段階的にリスクの小さい部分から進めていきましょう。
経理内製化は、以下の5ステップで段階的に進めます。
| ステップ | 主な内容 | ポイントの例 |
|---|---|---|
| 1. 現状分析と目的の明確化 | 外注内容や社内の経理体制を洗い出し、内製化の目的・目標を明確にする | As-Is / To-Be分析(組織やプロジェクトの現状/ 理想の状態) 課題の可視化 内製化する 業務範囲の明確化 |
| 2. 体制構築(人材採用・育成) | 経理に必要なスキルを定義し、社内の人員を確保・育成する | スキル要件の洗い出し OJTや研修制度の整備 業務分担の明確化 |
| 3. ツール・システム選定と導入 | 経理業務に必要な会計ソフトや管理ツールを選定・導入する | クラウド会計 RPA導入の検討 セキュリティコストの比較 |
| 4. 業務フロー設計とマニュアル化 | 各業務を標準化・マニュアル化し、属人化を防ぐ | 承認フロー 仕訳ルール マニュアルや手順書の整備 |
| 5. 外部委託からの移行計画と実行 | 現在の外注先からの引き継ぎと、内製化体制への段階的移行を行う | スケジュール管理 段階的な導入 定期的な効果検証と改善 |
まずは、現在の外注業務やコストを洗い出して現状を把握し、内製化する業務範囲を明確にします。現状と課題を明確化し、必要な人材像や育成、どのようなシステムが必要なのか見えてきます。
そのうえで、業務フローを設計しマニュアルを整備することで、業務の属人化を防ぎ、運用の安定化が図れます。運用の流れは以下が理想です。
1. 現状分析 → 2. 業務範囲の決定 → 3. 人材・ツール準備 → 4. 業務フロー整備 → 5. テスト運用 → 6. 本格稼働
内製化後も課題を見直し改善を重ねることで、経理体制をより強化できます。
経理内製化成功のための3つのポイント
経理の内製化は、計画的に進めれば大きなメリットをもたらします。持続可能な体制を築くためには、3つのポイントを押さえましょう。
内製化を成功させるためのポイントを解説します。
スモールスタートで段階的に進める
経理の内製化をすべて一度に切り替えようとすると失敗のリスクが高まります。
いきなりすべてを内製化しようとすると準備に時間がかかるだけでなく、導入時の混乱や担当者の負担増大、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。まずは、比較的定型化しやすく影響範囲の小さい業務から内製化を実施しましょう。
とくに経理担当者の経験や知識が浅い段階では、記帳代行、経費精算のみといった範囲から内製化を始め、運用を安定させながら徐々に対象業務を拡大させることが大切です。
すぐ結果につながらなくとも焦らずに、長期的視点で経理の内製化を進めていきましょう。
適切なITツールを活用する
経理業務の効率化や正確性の向上、ペーパーレス化を実現するには、自社の規模や業態、業務内容に適したITツールの活用が不可欠です。会計ソフトは業務効率化を最大化するにあたって必須ツールといえるでしょう。
例えば、クラウド会計ソフトを導入すると、次の業務の自動化が可能になります。
- 銀行口座やクレジットカード明細との連携による仕訳入力の自動化
- 請求書発行・送付機能、経営状況のリアルタイム可視化
- 法改正への自動アップデート対応
など
内製化を成功させるには単にITツールを導入するほかにも、運用マニュアル作成や研修を行うことで効率化だけでなく、業務の属人化防止にも役立ちます。
経理の内製化において、どのツールを導入すれば良いのかわからない方はAiPHA(アイファ)へお気軽にご相談ください。



既存ツールの選定から、御社専用のカスタムツール開発まで対応可能です。段階的なプロセスで、内製化の成功をサポートいたします。
定期的に業務見直して改善を行う
経理の内製化は、稼働後も定期的に業務プロセスや運用ルールを見直し、継続的に改善を行うことが大切です。内製化した後も新たに不要な作業や思わぬトラブルが起こる可能性があります。
従業員の意見や課題を見極めることで、運用マニュアルや業務内容は改善され、ノウハウが蓄積されていきます。内製化の実施後、特定の計算のみミスが多い、ルールの認識に齟齬が生まれているなどさまざまな課題に直面するでしょう。
その都度、ノウハウやマニュアルを更新する必要があります。内製化後も継続的に改善を重ねることが、組織体制の強化と成果に直結します。
経理の内製化で経営体制を強化しよう
経理の内製化は、単にコスト削減や業務効率化を実現する手段に留まらず、経営状況の正確な把握、迅速な意思決定、ガバナンス強化を通じて、企業全体の経営体制を強化するための重要な戦略です。
初期投資や業務構築の負担はかかるものの、計画的に内製化を実行すれば、組織力や経営力の強化につながります。
経理の内製化にお悩みの方は、当社「AiPHA(アイファ)」へお気軽にご相談ください。経理の内製化における課題や目標設定を一から行い、ツールの開発や体制の構築までを一貫してサポートいたします。



経理内製化の成功には適切な計画と段階的なアプローチが重要です。
課題分析から体制構築まで、安心してお任せください。