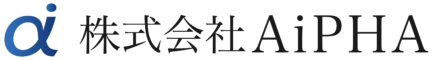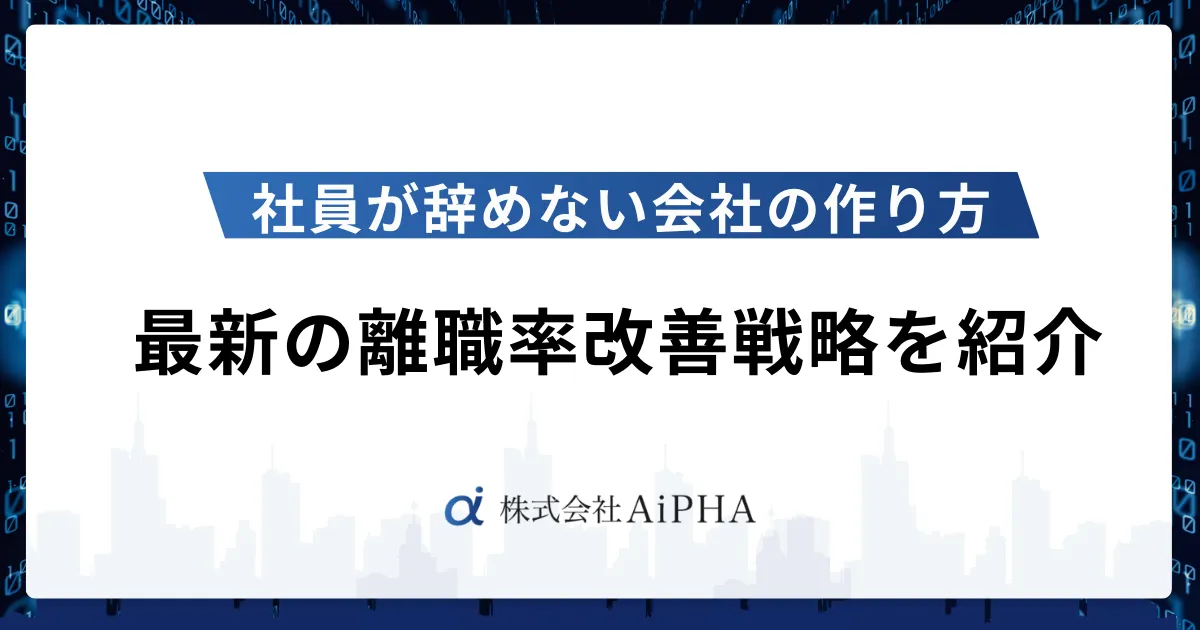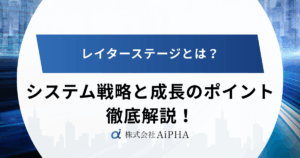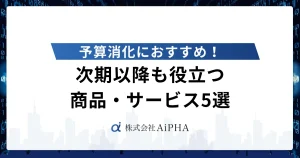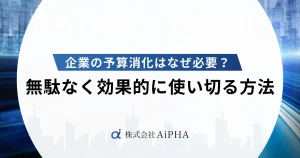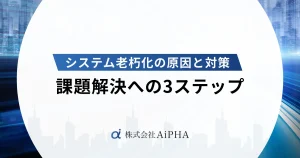離職率が高まると、企業の成長力は大きく損なわれてしまいます。
社員が辞めるたびに発生する採用コストや教育コストはもちろん、組織に蓄積されていたノウハウが流出してしまうのも深刻です。
そこで注目されているのが、AIやデジタル技術(DX)を活用した離職率改善の取り組みです。
従来からのやり方だけでは効果が薄いと感じている経営者や人事担当者の方に向けて、社員が辞めない会社を実現するための最新戦略を整理しました。
この記事では、本当の退職理由を理解する重要性と社員が辞めない会社づくりの施策について、AI・DXの活用を交えてご紹介いたします。
ぜひ最後までご覧いただき、自社にあったヒントを見つけていただければ幸いです。
なお、社員が辞めない会社づくりにAI・DX活用をお考えの場合は、当社「AiPHA(アイファ)」へご相談ください。ビジョン・戦略の策定からシステムの構築まで、包括的にサポートいたします。
 AiPHA代表 佐伯
AiPHA代表 佐伯「従来のやり方では離職率が改善されない」とお悩みではありませんか?
AI・DXを活用した人事戦略で、働きやすい環境づくりをサポートいたします。
社員が辞めない会社を作るには「離職理由」への理解が必要
退職時には本当の理由を伝えない社員が多いという事実をご存知でしょうか。
退職経験のある方の54%が「会社に伝えなかった本当の退職理由がある」と回答している調査結果※があります。その理由として最も多かったのは「話しても理解してもらえないと思ったから」(46%)でした。
※出典:エン・ジャパン「本当の退職理由 調査(2024)」
そのため、社員が辞めない会社を作りたいと思っていても、企業の施策が的外れになってしまうリスクがあります。
社員が辞めない会社を作るには、表面的な言葉だけでなく本当の退職理由を把握することが何よりも大切です。
真の問題を理解できれば、改善策もより的確になり社員の満足度を高めることにつながります。
社員が辞める本当の理由
社員が辞める背景には、多種多様な事情が潜んでいます。
しかし、冒頭で触れたように、退職時に表向きの理由しか聞き出せないことが多いのも実情でしょう。
ここでは、本当の退職理由の調査結果※をもとに、次の4つの退職理由について解説します。
- 人間関係が悪いから会社を辞める
- 給与が低いから会社を辞める
- 会社の将来性に不安を感じた
- 評価・人事制度に不満があった
※出典:エン・ジャパン「本当の退職理由 調査(2024)」
また、従来の対策が抱える課題や限界にも触れていきます。
人間関係が悪いから会社を辞める
本当の退職理由の第一位は「人間関係が悪い」が約半数(46%)を占めています。(複数回答可)
人間関係の悪化の主な原因はコミュニケーションエラーです。コミュニケーションが不足すると、誤解や行き違いが生じやすくなります。
例えば、上司が部下に資料作成を依頼したものの、進捗が滞っている状況で「なぜ早く相談しなかったのか」と叱責する場面を想像してみてください。部下は自力で解決しようと努力していたにもかかわらず、叱られることに不本意を感じ、上司からもっと早く必要な知識を教えてほしかったと考えるでしょう。
周囲の協力が得られず本音で話せない状況では「仕事がつらい」「上司に話しても理解してもらえない」といった不満が蓄積しやすい点も要注意です。
こうした人間関係の問題は、社員にとって最も深刻な離職要因になりやすいといえます。
給与が低いから会社を辞める
本当の退職理由の第二位として「給与が低いから会社を辞める」が34%を占めています。(複数回答可)
給与は単なる生活の糧ではなく、社員の貢献や価値に対する会社からの評価を表すバロメーターでもあります。業界水準を下回る給与や、努力や成果が適切に報酬に反映されないと感じる場合、社員のモチベーションは低下し、より良い条件を求めて転職を検討するようになります。
特に、同業他社と比較して給与水準が明らかに低い場合や、数年間昇給がない状況が続く場合は、社員の不満が高まりやすいと考えられます。
企業の収益や規模によっては賃金アップを大幅に実施するのは難しい場合も多いのが現実です。しかし、給与が離職の大きな要因となっている以上、何らかの対応策を検討する必要があるでしょう。
会社の将来性に不安を感じた
本当の退職理由の第三位として「会社の将来性に不安を感じた」が23%を占めています。(複数回答可)
経営方針が頻繁に変わったり、先行きが見えない組織体制だったりすると、優秀な人材ほどリスクを避けるため、早めに次の道を探し始めるでしょう。
また、業績の低迷やデジタル化・トレンドへの対応の遅れ、新しい提案が却下される古い企業体質なども、将来性に不安を与える要因となります。
将来性への不安を感じると、社員は自分のキャリア形成にも不安を抱くようになります。「このまま会社に残っていても成長できないのではないか」「会社自体が存続できるのか」といった懸念が生じ、より安定した環境や成長機会を求めて転職を決断するのです。
評価・人事制度に不満があった
本当の退職理由の第四位として「評価・人事制度に不満があった」が22%を占めています。(複数回答可)
公正性や透明性の欠如は、不平等感を招きやすいでしょう。評価・人事制度に不満を抱えた社員は、自分の努力や成果が正当に認められていないと感じると、モチベーションが低下します。
昇進や昇給の基準が曖昧なままだと、社員は自分の未来に希望が見出せず、退職を選択してしまいがちです。特に優秀な人材ほど、自分の価値を適切に評価してくれる環境を求める傾向があり、不満が蓄積すると転職を検討するようになります。
これらの離職理由に対して、効果的な対策を講じることが社員が辞めない会社づくりの鍵となります。次の章では、これらの課題に対する具体的な対応策について解説します。
社員が辞めない会社づくりのためにできること
社員の退職理由を理解したら、次は具体的な対策を講じる段階です。
離職を防ぐには、複数のアプローチを組み合わせて実施する必要があります。
ここでは、主要な離職要因ごとに人間関係や評価制度、さらにはキャリア支援など、具体的な対応策を解説します。
コミュニケーション促進・改善の取り組み
人間関係が悪い問題の多くは、コミュニケーション不足が主な原因です。
上司が早期に部下の不安や不満を察知し、必要であればハラスメントを防止する体制を整えることが重要です。
例えば1on1ミーティングや、定期的な面談制度を設けておけば、些細なトラブルも大きくなる前に解決できるケースが増えます。お互いの人生や価値観を共有し合うことで、部署や肩書を超えた信頼関係が育まれる可能性は高まるのではないでしょうか。
また、「褒める文化」を醸成することも重要です。例えば、上司が部下の日常的な善い行いを褒める、業務改善など良い行動に対しては管理者が表彰できる仕組みを導入するなど、ポジティブな職場環境を構築すると良いでしょう。このような取り組みは、社員同士の信頼関係構築に大きく貢献します。
適正な給与・福利厚生の整備
給与の低さも主要な退職理由の一つです。企業の収益や規模によっては賃金アップを大幅に実施するのは難しい場合も多いのが現実です。しかし、給与が離職の大きな要因となっている以上、何らかの対応策を検討する必要があるでしょう。
給与アップ自体が難しい場合でも、柔軟な働き方を支援する福利厚生の整備などで社員の生活を支えることはできるかもしれません。
たとえば、在宅勤務やフレックスタイム制を導入したり、育児・介護中でも働き続けられる環境を整えたりする取り組みが考えられます。
企業規模によってできることの幅は異なりますが、社員のライフステージに合わせた支援を行うだけでも、一定の満足度向上が期待できるでしょう。
キャリア支援・エンゲージメント強化
将来性への不安は離職の大きな要因です。社員が自社で成長できる確信を持てないと、将来性を感じられずに離職してしまうことが多いでしょう。
そこでキャリア支援制度を充実させ、社内外の研修プログラムや資格取得支援などを用意することも選択肢にいれましょう。企業の中には、社員の長期的な目標をヒアリングしながら、定期的にジョブローテーションを実施したり、エンゲージメント調査を活用してモチベーションの変化を可視化したりしているところもあります。
こうした取り組みは短期的にはコストがかかるかもしれませんが、優秀な人材が辞めない会社を作るうえで大切な投資となります。
評価制度の整備
「評価基準がわからない」「どこに向かって努力すればいいのかわからない」という声が社員から出るようなら、評価制度や人事制度を見直すサインです。
給与や待遇を一気に向上させるのが難しくても、公正で透明性の高い評価制度を導入することで、社員の納得感は大幅に高まります。
近年ではAIを活用してデータを集積し、上司の主観に左右されない評価指標を作る取り組みが注目されています。
データをもとに正しい評価を行えば、社員は「自分をしっかり見てもらえている」と感じられるため、仕事への意欲が上がりやすいでしょう。
AiPHA(アイファ)では、離職防止に必要な各種システムの開発・導入をサポートします。貴社の課題に合わせた最適なご提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。



離職防止には複数のアプローチを組み合わせることが大切です。
コミュニケーション促進から評価制度まで、包括的な解決策をご提案いたします。
AI・DXを活用した離職率の低い会社の作り方
昨今、働き方改革やデジタル技術の進歩を背景に、人事領域でもDXが進んできました。
単にコミュニケーションツールを導入するだけでなく、離職リスクを予兆段階で検知する仕組みを作り上げている企業も多くあります。
ここからは、AIを活用した離職防止の具体策や、評価データの一元管理事例について解説します。
AIを活用した離職防止プロジェクト
AIは離職防止において多様な形で活用できます。特に離職リスクの早期発見と対策に効果を発揮します。
日立ソリューションズでは、人事システムの「リシテア」と呼ばれる勤怠管理システムを開発しています。
これは社員の情報や勤怠データなどをAIに学習させ、働きすぎやストレスケアの対象者を抽出。いち早くケアを行い、離職リスクや求職者の発生を未然に防いでいます。
また、人事異動にもAIが活用されており、明治安田生命では1万人を対象に人事異動をおこないAI技術の活用を行っています。AIで社員の情報を学習した上で組織全体をみた時に最適な人員配置や構成を推論しており、人事領域の業務負荷を減らしています。
一般企業だけでなく、防衛省も人事評価や人事異動についてAIを使ったシステムを導入していく方針を示しており、今後よりAIの活用による離職率防止施策は注目を集めていくでしょう。
ただし、こうした仕組みを導入する場合はプライバシーへの配慮や情報管理が不可欠です。
データを使う側が「社員を監視している」と思われないよう、目的を明確に伝え、透明性を持って運用することに注意を払いましょう。
離職率を下げる施策として勤怠管理システムの導入をお考えであれば、ぜひ当社「AiPHA(アイファ)」へご相談ください。AiPHAでは、プライバシーに配慮した透明性の高い仕組みで、働きすぎの早期発見からストレスケア対象者の抽出まで、御社の人材定着をサポートいたします。



「社員を監視している」と思われないよう、透明性の高い運用が必要です。AiPHAでは、離職防止に役立つプライバシーに配慮したシステムを構築いたします。
評価データの一元管理と事例紹介
評価・人事制度への不満は離職の大きな要因です。
従来の感覚頼みの評価制度では、管理職の裁量や好みによって結果が左右される可能性もありました。
しかし、AIを活用した評価データの一元管理は、公平性の確保と業務効率化の両面で効果を発揮します。
IBMでは約37万人の従業員の評価にAIを活用し、成果やスキルの市場価値など多様な指標を分析して報酬決定の支援を行っています。AIはあくまで補助的な役割であり、最終判断はマネージャーが行う仕組みです。
モバイル大手のボーダフォン社は、約9万人の従業員の報酬決定プロセスにAIを導入し、3ヶ月かかっていた給与決定プロセスを15日に短縮しました。
また、松屋フーズホールディングスは、店長昇格試験に対話型AIの面接サービス「SHaiN」を導入。評価者によって評価基準が異なるという課題を解決し、統一的な基準での評価が可能になりました。「面接評価のバラツキをなくす」「面接のエビデンスが残る」といった効果が得られています。
AI活用がすべての課題を即解決するわけではありませんが、客観的かつタイムリーに社員の活躍を見つける体制を整えるだけでも、会社への愛着や自己肯定感を高める大きな助けになるでしょう。
離職理由を正しく把握し、最適な対策を講じる
社員が辞めない会社を作るためには、まず本当の離職理由を把握し、それに対する適切な対策を講じることが重要です。
離職する理由としては、以下の4つが主要因とされています。
- 人間関係の悪化
- 低い給与水準
- 会社の将来性への不安
- 評価制度への不満
これらに対して、適切な対策を講じることが「社員が辞めない会社を作り」おいて重要です。
コミュニケーション促進や福利厚生の充実、キャリア支援制度の整備、そして透明性の高い評価制度の構築など、できることはいくつもあります。
さらに、AIやDXを活用することで、離職リスクの早期発見や公平な評価の実現が可能になります。社員一人ひとりの声に耳を傾け、最新技術も積極的に取り入れながら、働きやすい環境づくりを目指しましょう。
AIを活用した人事評価や業務効率化にご関心がありましたら、ぜひ当社「AiPHA(アイファ)」にご相談ください。
お客様の企業文化や業務フローに最適化されたAIソリューションを提供いたします。



「本当の離職理由がわからない」とお困りなら、AI分析で見える化しませんか?
データに基づいた効果的な離職防止策をご提案いたします。